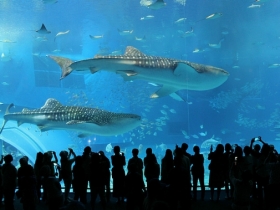20代から30代の地元のイケメンが作る男の豆腐

豆腐の製造が本格的に始まるのは夜中の1時頃。光さんと光さんの両親が大豆を水に漬け込んだり、豆を煮たりの作業があるので、スタッフが出勤する前も帰った後も、豆腐屋に人の気配がないことはほとんどないそうです。

製造が始まってしばらくすると、工場の中は熱気でムンムンしてきます。畳10枚ほどの小さなスペースで20〜30代の男達が肩を並べて黙々と働く光景は見ていて清々しい眺めです。三つの釜がフル回転。手際よく、次々とおいしそうな豆腐ができていきます。

商品は島豆腐とゆし豆腐の2種類のみ。味の自慢は三つもあります。柔らかい、なめらか、クリーミー。食べてみると確かに、濃厚な味と豊かな香りとともに、舌触りのよい独特の質感が伝わってきます。それでいて、県外の絹ごし豆腐のつるつる感とはまったくもって違う沖縄の島豆腐らしい、重厚さとコクもしっかり。
3つのこだわりがおいしさの秘密


「三つのこだわりにはそれぞ工夫があるんです。柔らかさはにがりの打ち方とかき混ぜ方で変わります。温度も影響しますが、同じ温度でもにがりを打つ高さやにがりが落ちる場所によってすごく違ってくるんです。二つ目のこだわりのなめらかさは、豆乳の濾し方と型に流し込む時の力加減で決まります。

最後のクリーミーさは、豆乳の濃度です。濃度を上げるには水分を飛ばさなくてはいけませんが、火のかけ方を間違うと、焦げてしまって使いものにならなくなります。

『柔らかくて、なめらかで、クリーミーな島豆腐を作りたい』と宣言した時は周りから『そんなの無理!』だと笑われました。目指す豆腐がある程度形になるまでに3年はかかりましたよ。実際にしばらくは作っては捨て、捨てては作っての繰り返しでした」

「豆腐は生きものだ」という光さん。豆乳、にがり、塩。ものすごくシンプルな素材で作る食べものだからこそ、毎日変動があるようです。「心の中で大豆と会話をするくらい」丁寧に素材のようすをさぐり、ご機嫌に合わせて調整をする。違うものができた時には、工程のどこで何が違ったのか素早く推理して解決しなくてはならない。なぜなら「同じようにやっても、できるものはほぼ毎日違うから」。
「幻の豆腐」を目指して

ゆし豆腐
「こだわりがないと始まらないですよね」と光さん。デザインやものづくりへの興味が早いうちから芽生え、高校を卒業してからは県内のデザイン系専門学校へ進学。学校に通いながら家業の豆腐店を手伝ううちに配達先でお得意さんの要望を聞くようになったのだそう。「何かに興味を持つとどっぷりはまってしまう性格」の光さんはお客さんの声になんとか答えたいと思うように。

ゆし豆腐
「製造の手伝いをしながら、こうしたらどうだろう、ああしたらどんなだろうかと考えるようになるまでにそれほど時間はかかりませんでした。専門学校を卒業してしばらくして、自分の豆腐を作ることに決めました」
幸いお母さんとお父さん達が豆腐を作るのは早朝からお昼まで。午後からは工場を自由に使うことができたのです。のめり込む性格はしばらくすると再び新たな決断をもたらすことになったのだとか。

「お客さんの要望に沿った柔らかい豆腐を作り始めて6年ほどたったころ、『家業を本格的に引き継いで新たなスタートを切りたい』と親父に持ちかけました。最初は慎重だった両親でしたが、熱意が伝わりお店を継がせてくれたんです。実家の屋号の宇那志をもらって、母と父の大城豆腐店が宇那志豆腐店として生まれ変わったんです」
2011年に新創業をしてから今年で5年。
「これまで豆腐を作る中で、柔らかくて、なめらかで、クリーミーなだけでなく、さらに甘みがあって、型崩れもしない完璧な豆腐に2回だけ出合ったことがあるんです」
目を細めて語る姿が印象に残っている光さん。「幻の豆腐」を再現しようと、今日もおいしい豆腐作りに励んでいるに違いない。